エドワード・O・ウィルソンによる著書「人間の本性について」の読書感想です。9章で構成された書籍であり、章ごとに感想を書いています。
(本書の内容)
人間の本性を自然科学(生物学)において考察しようとするもの
書籍紹介
著者:エドワード・O・ウィルソン
第一章 ジレンマ
わたしたち人は、他の動物と同様に自然選択により生まれてきた存在であり、特別の目的地はない。人間の「心」というものも、生存と繁殖のための装置でしかない。
人間の本性を生物学的な視点から考えるとき、こうしたジレンマに直面するだろうと著者は指摘している。
このように指摘されてしまうと、誠実に生きること、世のため人のために働くこと、人格を磨くことの価値が損なわれてしまうように感じる。
でも、人間だけが神のつくった存在であり、他の生物とはまったく別物という根拠は確かにない。
人間という存在を特別視せず、生物学の観点から分析することで、私たちの期待や願望を排除した本当の「人間の本性」が見えてくるのだろう。
第二章 遺伝
人間のあいだ(個体間)においては、遺伝子の多様性がみられるらしい。そして私たちは人間は、遺伝的制約(生まれ)と、文化的環境(育ち)によって形成されている。
人間の多様性が、私たちの持っている遺伝子の多様性によるところが大きいのならば、自分の価値観を他者に押し付けることは意味がなさそうだ。遺伝的な多様性を認めてこそ、人間社会はシナジーを発揮し、大きく発展するのだろう。
第三章 発達の過程
私たちは遺伝的プログラムにより、いわば自動的に言語などを習得しているようだ。新品のスマホやパソコンを立ち上げたときに、必要なプログラムが自動更新されるようなイメージだろうか。
人間はまったくの白紙で生まれるのではなく、遺伝により諸能力を備えている。性格の諸特性は遺伝の影響は小さいようだが、知的能力や感覚、運動場の諸能力は遺伝によるところが大きいようだ。
この事実をどう受け止めるべきだろうか。くじ引きではずれを引いたような気持ちで、知性や身体的能力の低さを嘆くのだろうか。それとも、遺伝的な制約があることを自覚しつつも、その能力をフルで使うため、知性などを伸ばす努力を惜しまず日々を過ごすべきだろうか。
一度きりの人生だから、生まれ持ったもので勝負するしかない。持っている武器がしょぼくても、その性能を高める努力はすべきだと思う。
第四章 社会進化と人間の本性
人類の歴史は長く、99%以上の期間は狩猟採集民として生きてきた。私たちの遺伝子は、狩猟採集民時代の環境において有利であった特性を持っており、それはいまなお堅固であるという。
私たち現代人は、極めて高度な科学技術を持ち複雑化した社会に生きているにもかかわらず、狩猟採集民時代の遺伝子を使って生きているのだ。
世の中で起こる不祥事は、古代から受け継がれた遺伝子に抗うことのできなかった人が起こす問題なのかもしれない。できるだけ財産をためたい、繁殖の機会を多く持ちたいといった気持ちが、世の中のルールを破ってでも悪い行動をさせてしまうのだろう。
一方で社会に大きく貢献する人たちがいる。利他の心をもつ人々も世の中には多いものだ。これも古代人から受け継いだ遺伝子によるものだろうか。
いずれにせよ、不祥事を起こす人(悪い人)よりも、社会貢献する人(良い人)が世の中に増えたほうがいい。それは、良い人のほうがより多くの子孫を残すことで達成される。しかし、世の中そうとは限らない。現代においては、誰もが子供を多く作らない。これは自然淘汰において大きな問題かもしれない。
第五章 攻撃行動
私たち人間の遺伝子は、攻撃行動を学習するようプログラムされている。テリトリー性や集団内での優位性を高めるために必要だった攻撃行動は、今となっては悲しいだけの戦争や犯罪を引き起こすものであり、できるだけ手放したい習性である。
しかし人間の本性として備わった習性であり、人間には暴力性があることを意識し、それを制御しなければならないようだ。
私自身はどうだろうか?子供同士のけんかや、親への暴言暴力を抑え込むため、子どもたちをチカラで鎮圧する時期があった。これも人間の本性として自然な行動だったのだろうか。成人男性のチカラを家族に見せつけることで、家庭内での優位性を高めようとしたのかもしれない。
しかしこのようなやり方では、家庭内での問題を何一つ解決できなかった。子供に対して、話をちゃんと聞く姿勢、理解しようとすること、努力を認めること、こうした対応のほうがよほど効果があった。
攻撃行動はやはり制御すべきしろものだと思う。
第六章 性
男女はもちろん平等だが、男性と女性には気質上・身体上の差異があり、遺伝的にも差異があるらしい。女児がおままごとを好み、男児は無鉄砲な遊びをすることは、育てられる環境ではなく、遺伝的なものがあるようだ。
社会では女性の管理職の登用が増えている。しかし私の職場では、昇進を望まない女性は多い。女性を無理にリーダーに担ぎ上げても(その女性にリーダーとしての素質が十分にあるとしても)、必ずしも良いとは言いきれないのかもしれない。
男女平等を追求するのではなく、男女それぞれが、いや、男女関係なく一人一人ユニークな存在である個人が、それぞれに幸福な生き方ができればいい。出世に関しては、機会だけは平等に与えられれば、それでよいと思う。
性活動は、生殖や繁殖、快楽を主目的としておらず、男女の(あるいは同性間での)絆を深めるためにある、という見解が本書で述べられている。確かに、性活動においては避妊を行うことが多い。子供は1人か2人で十分と考えるカップルは多いのではなかろうか。
そして快楽も、性活動を促進するための機能にすぎず、性活動の主目的はあくまでカップルの絆を深めることにあるそうだ。実際の人々の意識としては、快楽目的が先行しているようにも思うが…。
同性愛は遺伝的なものであり、しかも種の繁栄に役立っているという見解も述べられている。古代においては同性愛者は親族の子育てなどをサポートしていたそうだ。同性愛者は知的にも優秀で組織の要職に就くことが多いらしい。
また、同性愛の遺伝子は実は多くの人々が持ち合わせており、ただ、それを発現するのは少数の人だけのようだ。私自身は同性愛者ではないが、その遺伝子は持っているかもしれない。ある日、突然に発現する可能性もあるのだろうか。
以上のような見解は、私自身のパラダイム(ものの見方)を大きく変えるものとなった。これまでも同性愛者を差別してきたつもりはないが、同性愛者を理解するうえでの新たな視点を授けられたのだ。
第七章 利他主義
自分を犠牲にして相手に奉仕する行動、すなわち利他的な行動は、実はそのほとんどが、究極的には利己的なものであるらしい。真に利他的な行動は、ごく近い血縁関係の者に対して行うケースに限られるという。
「利己的な利他行動」と「真に利他的な行動」。前者は偽善のにおいがし、後者は真の愛情を感じさせる。
しかし「真に利他的な行動」こそが文明の敵らしい。これは大きな驚きだ。実は「利己的な利他行動」のほうが社会的には良いらしい。
「真に利他的な行動」は、身近なものたちを優先するあまり、よそもの(他者、他の部族、他国の人々、他の人種)をないがしろにするのだ。これは社会においては争いの種となる。だからダメなのだ。
なんだ、利己的って悪くないのか。利他行動の裏に見返りを求める気持ちがあっても、やましさを感じる必要はない。
他者に親切にすることで、親切のお返しを期待できる。自分の良心に従って生きれば、自分自身の人生が豊かになる。「情けは人の為ならず」の精神で良いのだ。
第八章 宗教
いまや科学は、宗教・信仰を解説し、その立場を突き崩しつつある。信仰心を持とうとするのは人間の本性であるが、神や神話、聖なるものは人間がつくりだしたものにすぎない。こうして考えると、宗教というものの価値が大きく下がってしまうように感じる。
しかし信仰心の厚い人たちの中には、その教えを守ることで豊かに暮らしている人もいる。宗教を心から信じることができる人は、それはそれで幸せだろうし、立派な生き方であるように思う。
第九章 希望
著者はさいごに、科学的唯物論、進化こそが壮大な物語で、畏敬の対象となるべき神話だと説明している。
空間も時間も、“存在する”ということも、とても不思議なことだ。これらを科学のチカラで解明しようという努力は、人間の本性を解明しようとする努力と、同じことなのかもしれない。
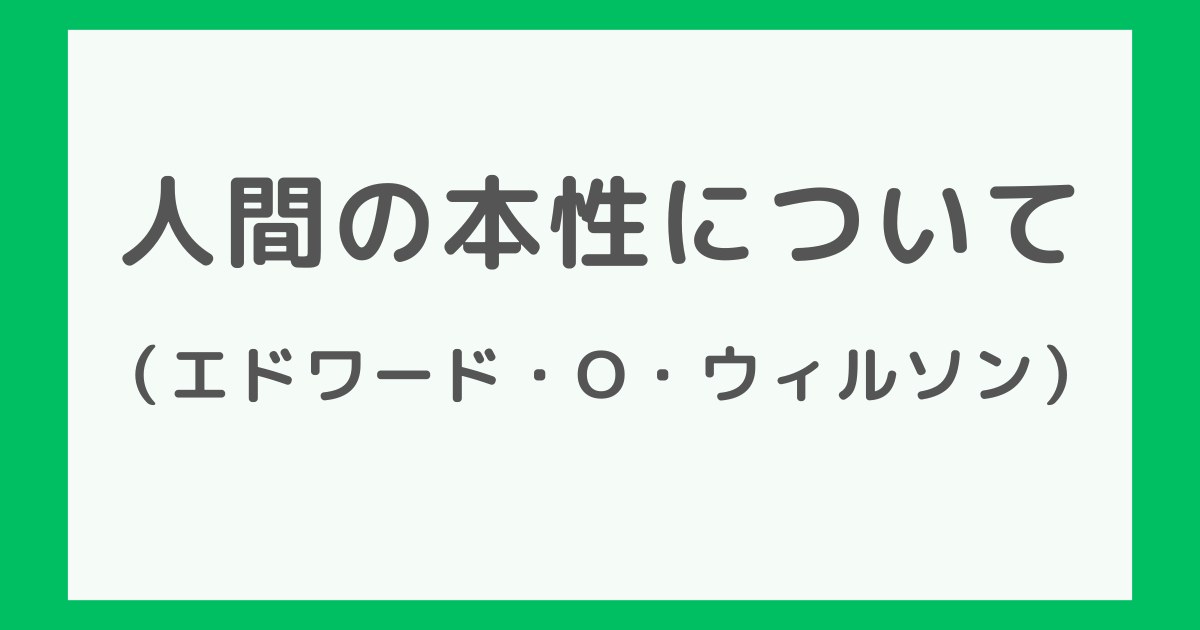
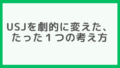

コメント